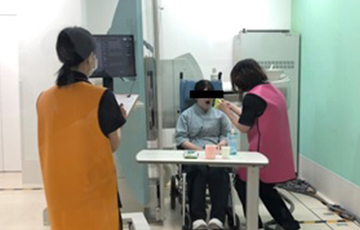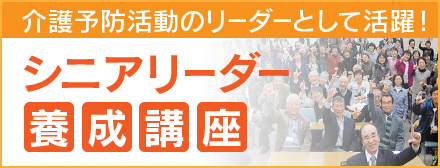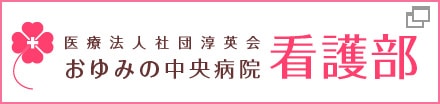言語聴覚士とは?
ことばによるコミュニケーションに問題がある方の本質や発現メカニズムを明らかにし、対処法を見出すために検査・評価を実施し、必要に応じてリハビリテーションや援助を行い、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職です。また、摂食・嚥下(食べ物を見て、口に入れ、噛んで、飲み込むまでの過程)の問題にも専門的に対応します。
言語聴覚士は、患者様の生活の質を向上させる重要な役割を担っています。例えば、言葉での意思疎通が難しかった方が、治療を通じて家族と会話できるようになる瞬間や、摂食・嚥下機能が改善し、好きな食べ物を再び楽しめるようになる瞬間は、大きなやりがいを感じる場面です。
例えば、摂食・嚥下機能障害を持つ患者様に対しては、誤嚥リスクを評価します。その後、飲み込みやすい食形態や姿勢の指導、筋力強化などのリハビリを行い、安全に食事を楽しめるよう支援しています。
一方、高次脳機能障害を持つ方には、失語症の改善を目指し、日常会話の練習や視覚記憶を向上させるトレーニングを行っています。
当院の言語聴覚士の特徴
- 女性6名、男性2名、計8名在籍 *令和7年1月時点
- 認定セラピスト2(高次脳機能障害、摂食嚥下障害)
- 認定研修補助制度あり
- ボバース研修(毎月)
定期的に実施しているカンファレンスを通じて他職種と意見交換を行い、患者様に最適なリハビリプランを提供しています。学会参加についても支援をしており、スタッフ同士の交流も盛んなため、互いに学び合う風土があります。
また、当院では言語聴覚士としてのスキル向上を支援する環境を整えております。
認定研修補助制度を活用して専門知識を深める機会を提供し、毎月のボバース研修では摂食・嚥下機能障害や高次脳機能障害に関する最新の治療法を学ぶことができます。
また、経験豊富な先輩スタッフからの指導を受けられるため、臨床経験が浅い方でも安心して働けます。
当院の言語聴覚療法の特徴
摂食嚥下機能障害(飲み込みの障害)が多い
ケースによっては嚥下造影検査を実施し、評価、リハビリを実施しております。
当院では、脳卒中後の失語症患者様が、1年間のリハビリを経て簡単な会話が可能になり、社会復帰された事例があります。摂食嚥下障害においては、嚥下造影検査を活用したリハビリで、誤嚥性肺炎を予防しながら安全に食事を楽しめるようになった高齢患者様も多くいらっしゃいます。
高次脳機能障害患者
検査道具は各種揃っています。
- SLTA
- SALA
- 重度失語症検査
- SDSA
- BIT
- CAT
- Benton 視覚記銘検査
- WAIS-Ⅲ
- RCPM
- S-PA
- TMT-J
- その他スクリーニング評価

失語症や摂食嚥下障害に対しては、初診時にSLTAやSALAなどの検査を実施し、患者様の状態を詳細に評価しております。その結果に基づき、嚥下造影検査を行う場合もあり、安全で効果的なリハビリプランの提供が可能です。治療中は経過を定期的に評価し、最適な方法を柔軟に取り入れています。
患者様の状態に合わせて検査を実施し、リハビリテーションを行います。必要に応じて退院後もフォローを行っています。
他職種との連携
当院では、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士など、他職種と連携して患者様に最適なケアを提供しています。例えば、嚥下造影検査では放射線技師や医師と協力し、検査結果に基づいて食事の形態やリハビリ計画を策定します。こうしたチーム医療を通じて、患者様の生活全体を支える総合的なサポートが可能です。